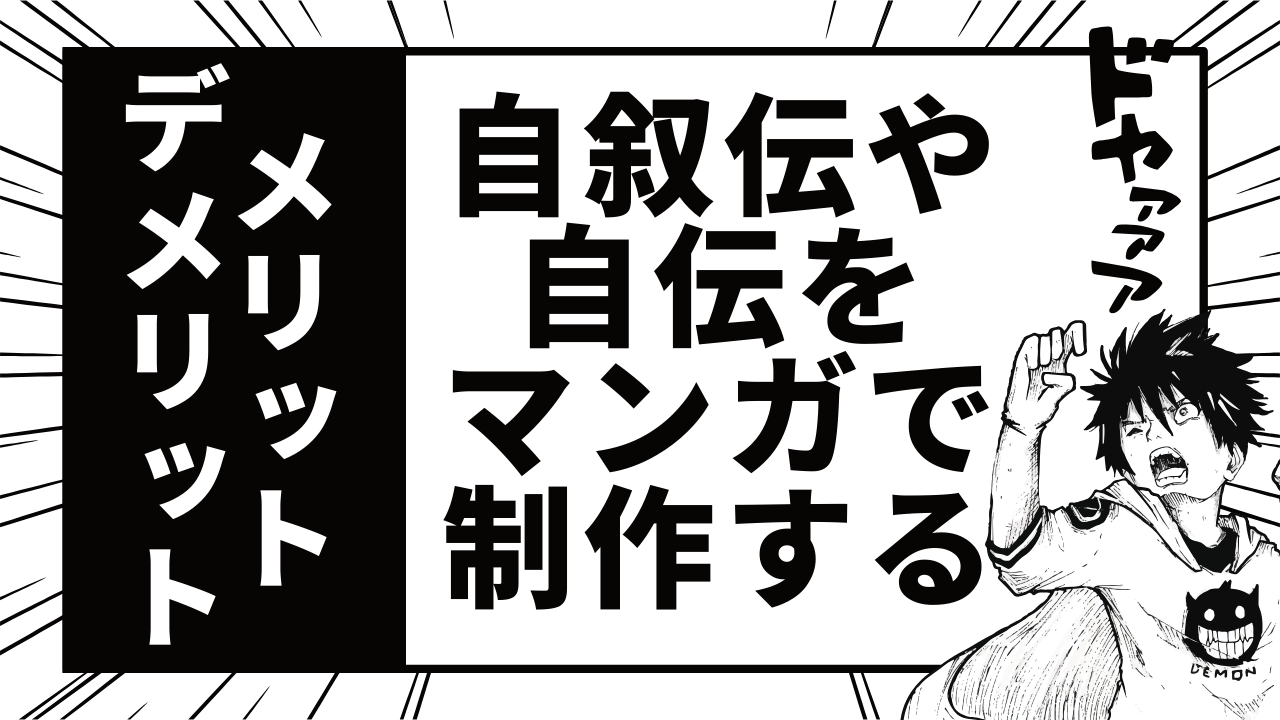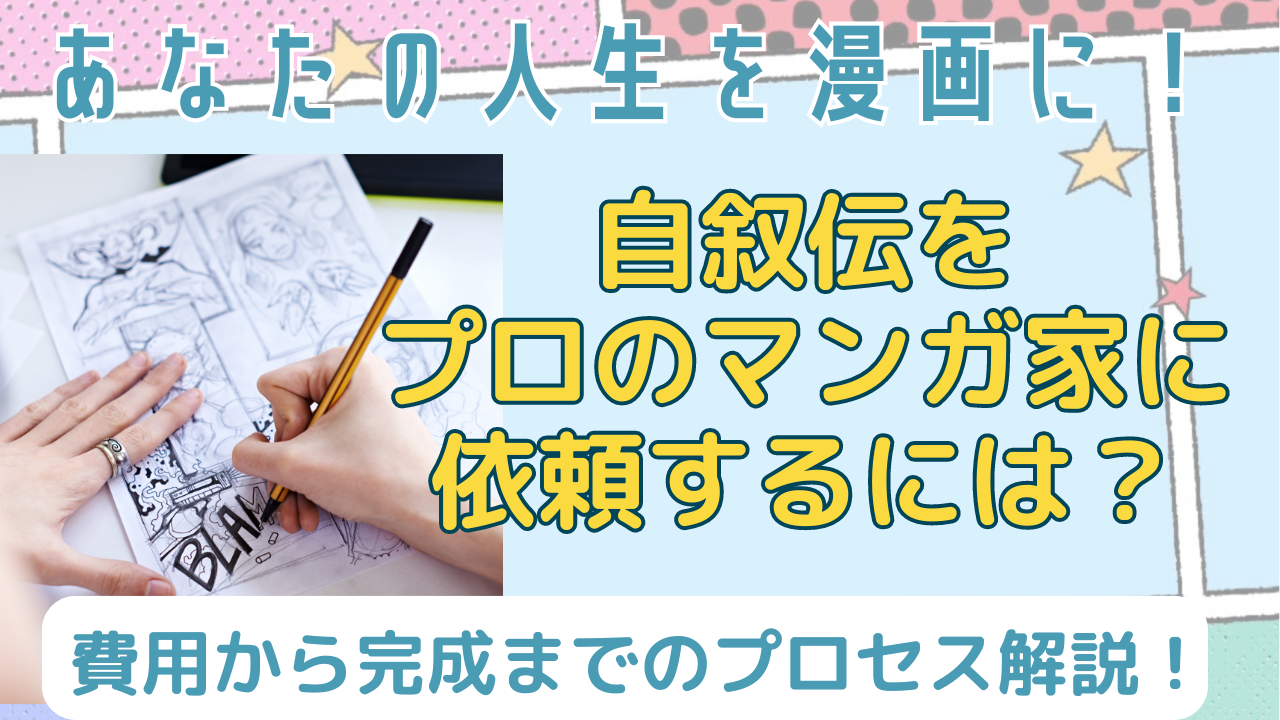
「これまで歩んできた自身の人生を漫画として形に残したい」と思われている方は少なくはないです。
しかし、文章に残した所できっと誰も読んでくれません。苦肉の策として漫画にすれば楽しんで読んでくれるかもと思っても
- 一体どのように制作すればいいのか?
- 漫画家さんに頼むとしても膨大な量になってしまうのではないか?
- 費用はどれほど掛かるのか?
など沢山の疑問を前に現実的ではないと考える方も多いでしょう。
本記事では、漫画自叙伝として自身の人生を残すための具体的な方法や、作成をプロに依頼する場合のメリットや費用について解説しています。
実際に自身のエピソードを漫画として残した経験がある筆者が、マンガ作成中に感じた自叙伝のメリットや具体的な作成方法について詳しく説明していきます。
これから自叙伝を残そうとされている方や漫画家を目指そうとされている方にとって、有益な記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 漫画自叙伝とは?

ここでは、漫画自叙伝の説明と利点についてご説明していきます。
漫画自叙伝の説明
漫画自叙伝とは、自身の物語を漫画で書いたもので、自伝や自分史とも言います。
生い立ちや経験、エピソードを思い出のままに描くと思われがちですが実は違います。
生まれや幼少期から書き始め小学生からの学生時代、現在という流れでは進みますが、そこに演出という要素が入ります。
自叙伝は、これまでの人生の流れに沿って執筆が基本ですが、全てを描こうとすると誰がやっても何十巻にも及ぶ超大作になってしまいます。ですので、漫画自叙伝の場合は、
- 制作の目的
- 自分の考え方を残す
- 家族に伝え、残したいメッセージがある。
- 会社・友人・顧客に伝えたいメッセージがある
など、伝えたい事をいくつか具体的に想像し、それらのメッセージが最も伝わりやすいエピソードを人生からピックアップし、制作していきます。
例)
Aパート
幼少期(小学生の頃のエピソード):自分の考え方を描く
Bパート
学生時(高校生の頃の恋愛エピソード):家族へのメッセージを描く
Cパート
会社創業時のエピソード:会社・友人・顧客へのメッセージを描く
それらを最終的にDパートでまとめるという構成がオーソドックスな形式となります。
自叙伝を書く一番のポイントは「自由に書く」ことです。
漫画自叙伝の利点
漫画で自叙伝を描くメリットで一番大きいのは何より「手に取って貰えやすい」事です。
知らない人の自叙伝であっても表紙や絵柄などが気になれば読者は気軽に手に取ってくれます。それが家族や知人の物であればほとんどの人が読んでくれます。そこが、文章で自叙伝を書く場合との一番の違いになります。
また、漫画にするという事はエンターテイメント化するという事ですので「読むめんどうくささ」を大きく減らす事になり、それは自分の自叙伝を気軽に人に勧める事を可能にします。制作の副産物的なメリットとして、自分や家族のこれまでの人生を見直せるため、新しい目標や生きがいを見つけるきっかけにもなります。
2. プロに依頼するメリット

漫画制作を依頼する際、プロの漫画家に依頼をしたいがプロに依頼する利点が分からないと思われている方は多いと思います。
なのでここでは、プロに依頼するメリットについてまとめましたのでご覧ください。
専門知識: プロの漫画家やシナリオライターのスキル
漫画作成を行う際にはプロの漫画家やシナリオライターがいます。
プロのマンガ家は、漫画を描くことを仕事にしている方です。漫画を描くには多くのプロセス(工程)があり、それらをすべてこなすのがプロの漫画家です。
シナリオライターは漫画業界では「漫画原作者」と呼ばれ、漫画のストーリーや演出方法を漫画家の前に考え、漫画家に提供する事を仕事としています。
漫画を描く技術を持ち合わせた方も少数いますが、そのほとんどが文章制作により漫画家にアイディアを提供するスタイルで仕事をされています。
品質: プロによる高品質な作品制作の利点
漫画自叙伝を作成する際、プロの漫画家へ依頼した場合得られるメリットを説明します。
プロの漫画家は、安定したクオリティで漫画を描いてもらえます。
「面白い漫画」「多くの人が読みやすい漫画」を求めるならプロに頼む以外に方法は無いと思います。「文章力の高さ」も、プロの漫画家の魅力の一つです。
時間の節約: プロに依頼することで得られる時間的余裕
漫画自叙伝を作成する際、どうしても時間はある程度かかります。
特に時間の使い方としてもったいないのがプロセスが何も進んでいない時で、それが漫画家の経験不足から来るものである場合本当に時間の無駄です。
しかし、プロの漫画家に依頼すれば、時間(スケジュール)を守った作業を進められます。
3. 漫画家の選び方

漫画家に依頼するメリットが分かり、依頼しようと思っても
直接漫画家に依頼するか企業を通してプロ漫画家へ依頼するか
のどちらがいいのか初めて依頼される方には判断が難しいです。
漫画家に直接依頼するのと企業を通した依頼の漫画家それぞれのに依頼するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
直接漫画家に頼むメリット・デメリット(ポートフォリオ、レビューサイト、SNSなどで見つける)
フリーランスや個人の漫画家に直接依頼するメリットは、制作会社を仲介しないため比較的安く依頼できる点です。もちろん高い方もいますが制作会社の取り分がかからないという意味です。
また、イラストタッチやテイストなど自分で好みの漫画家を幅広く探せる点もメリットの一つにあります。
一方でデメリットは、漫画家の選定から企画作りなど漫画制作の経験のないあなたが多くの事をしなければいけない事です。
そのほかにも、制作作業が漫画家一人によって行われるため、完成イメージとのミスマッチが起こりやすくなります。
制作物の進捗状況の確認などもをすべて依頼主が行う必要があるので、結構大変です。
企業を通して漫画家に頼むメリット・デメリット
多くの会社では、漫画の制作に関わるディレクション(仕事の管理)をしてくれる人が担当となり作品制作はもちろん、制作工程管理やトラブル発生などのイレギュラーな事態に即座に対応できるようになっています。
個人の漫画家に直接頼む場合と一番の違いはディレクターという役割がいる事で漫画制作に関わる2者(クライアント・漫画家)の舵取りをする役割がいるという事です。 以前の記事にも書きましたが漫画制作はクライアントにも大きな苦労が生じます。正直に言ってディレクターに舵取りをしてもらえなかったら、ほとんどの漫画は制作途中で中止になるのではないかと感じます。
またデメリットとしては、多くの事に対応してくれるディレクターが入る分、どうしても費用が割高になってしまいます。しかし、自分がイメージするマンガのタッチに合わせマンガ家を選定してくれるので、自身で漫画家を探す手間など多くの手間がかなり小さくなります。資金的に問題が無ければ、最終的に漫画制作にかかる総額や漫画の出来を見るとかなりお得なサービスです。
ただし、それだけにディレクターの実力により漫画の出来や最終的な費用にも大きな差が出る事にお気を付けください。
優秀なディレクターがいるプロのマンガ家在籍のおすすめ企業はこちら!→ https://eggbooks.net/
4. 漫画制作依頼の具体的な手順

早速漫画制作を依頼しようと思っても、まず何から始めれば良いのか疑問に思われる方も多いでしょう。
以下で、漫画制作依頼の具体的な手順について解説しますのでご覧ください。
初回相談: 初期相談での確認事項(アイデア、スケジュール、予算)
まずは、依頼内容をリクエストします。
企画や制作意図、完成イメージを伝え、どのくらいの期間で作成可能か企業側との入念な確認が必要です。漫画家などもこの段階で決まると話がスムーズに進みますが、企画自体がしっかりとしていない場合は個人の漫画家や漫画制作会社と企画からの練り込みになります。(費用に加算される可能性あり)
また、予算に関しては自身が考える完成イメージと、イメージに合わせた予算をはっきり伝える必要があります。
契約書の作成: 契約内容(納期、費用、権利、修正回数など)
初回面談でお互い確認事項に合意し契約となった場合、契約書を作成する必要があります。
契約内容は事前に決めた納期や制作費用、漫画の修正回数などです。また、著作権についてもしっかり確認し、契約するようにしましょう。
大まかな制作プロセス
- プロット(ストーリーやキャラクター作成)
プロットは漫画の骨組みで漫画のおおまかなあらすじを文字や絵でまとめたものを指します。 - ネーム(絵やコマ割、セリフを大まかに決め漫画全体の流れを決める作業)
- 下絵(ネームをもとに原稿用紙に絵を書き始める)
- ペン入れ(下絵の清書)
- ベタ・ホワイト(ベタ塗、はみ出しや書き間違いの修正を行う)
- トーン貼り(影や色などの効果を表現する)
- 最終チェック
5. 費用の見積もり

漫画制作を依頼する中で、一番気になるのが費用や料金だと思います。
クオリティが高い作品を制作してほしいが、予算に限りがある。というケースもあると思います。
そこで、制作にかかる基本的な費用についてご説明します。
基本料金: ページ単価やプロジェクト全体の費用
実際の金額は、ページ数や内容、原案の有無、制作難易度等により異なります。
おおよその料金はこちらです
- マンガ制作会社 15000円~30000円
- 個人漫画 8000円~15000円
- 有名な漫画家 4万円〜
- SNSで有名な漫画家 50000円
- クラウドソーシング 6000円~12000円
- マンガ制作会社 20000円~40000円
- 個人漫画家 12000円~20000円
- 有名な漫画家 要相談
- SNSで有名な漫画家 要相談
- クラウドソーシング 8000円~15000円
追加費用: カラー、特別な描写、修正回数に伴う追加料金、漫画はモノクロとカラーで料金に差が生じます。
イラストには料金設定がいくつかあり、スーパーリアルや細密性など手間がかかるイラストには追加料金がかかってきてしまいます。
修正回数は、上記で説明した契約内容を決める際に何回まで無料で修正可能か、1回の修正につきいくらの追加料金が発生するかも企業側と入念に確認しておく必要があります。
支払い方法: 支払いスケジュールと方法
支払いのタイミングは、「依頼成約時」「打合せ後」「納品前・後」とさまざまなパターンがあります。
支払い時期は、企業側にあらかじめ確認しておくといいでしょう。
支払い方法は、銀行振込/PayPayや楽天Payなどの電子マネー/オンライン決済システムPayPal/その他アプリや現物支給など様々ありますので、そちらも確認しておきましょう!
6. コミュニケーションの重要性

漫画制作は、制作を依頼して終わり!ではありません。制作途中でも作品の進捗状況や納品に間に合うか、修正点など漫画家と、こまめな連絡は必要です。
ここでは、定期的な連絡についてご説明します。
定期的な連絡: 進行状況の確認と修正点の共有
契約時に大まかなストーリーや、イラストタッチなどお互いに確認は行っています。
しかし、制作途中でも完成時に「思っていたのと違う作品になってしまった」とトラブルにならないよう、制作中も依頼者と漫画家で進捗状況、内容確認を行いましょう。
途中で、修正点が出た場合は追加料金が発生しないよう、なるべく契約時に交わした修正回数の範囲で修正してもらえるようにするといいでしょう。
フィードバックの提供: 効果的なフィードバックの方法とタイミング
漫画家へのフィードバックは具体的に修正理由をしっかり伝えるようにします。
おおまかな指示だけでは、相手のモチベーション維持にも関わり、作業効率の低下に繋がりかねません。
フィードバックは具体的な内容を伝えると同時に、参考資料も添付するとより正確に完成イメージを伝えられます。
フィードバックのタイミングは「遅すぎず早すぎず」を意識するようにするといいでしょう。
フィードバックを受けた際、軌道修正する余地があるときがベストタイミングですが、タイミングを判断するのは困難です。
そのため、日頃からこまめに連絡をとり、フィードバックのタイミングを逃さないようにしましょう。
7. 完成までのタイムライン

漫画1コマが完成するまでにいくつか段階があり、すべて重要な作業です。
以下で完成までの手順についてご説明しています。
スケジュール管理: 各段階のタイムライン(ストーリーボード、ラフ、下描き、ペン入れ、仕上げ)
漫画完成までには段階があり以下の順で進みます。
- プロット(キャラクターデザインや設定を決め、ストーリーのあらすじをまとめる)
- ネーム(プロットで考えたストーリーを基にページ数を決めて1ページごとのコマ割りや構図、セリフを簡単に描いていく)
- 下描き(ここで描き込みすぎると、ペン入れの際に迷ってしまうため、見やすい下描きにしておく)
- ペン入れ(輪郭などの主線はGペン、瞳や背景などの細かい線は丸ペンと使い分ける)
- ベタ塗(マジックや筆ペンで黒く塗りつぶすことを「ベタ」、髪の毛などつやがあるベタのことを「ツヤベタ」という)
- トーン貼り(ベタではない個所はスクリーントーンを使用する。力を入れすぎて下の原稿まで切らないよう注意が必要。)
- ホワイト(線のはみ出し部分やミスした個所を修正する)
- 完成(プロット〜ホワイトまでで1コマ完成)
納品前の確認: 最終チェックと修正点の確認
作品が完成したら納品前に必ず最終チェックと、修正点の確認を行い納品です。
8. 出版と配布

漫画が完成し、早速出版と配布を行う際、自費出版と商業出版の違いも認識しておく必要があります。
以下で自費出版と商業出版の違いについてご説明します。
出版オプション: 自費出版と商業出版の違い
自費出版と商業出版について分かりやすく説明すると、自分で費用を出して出版するのが自費出版、プロの作家が出版社を通して商業目的で出版するのが商業出版です。
マーケティング戦略: 自叙伝漫画を広めるための方法(SNS、イベント、ウェブサイト)
自叙伝漫画を世に広めたいと思っても、作成しただけではなかなか認知してもらえません。多くの方に見てもらうためにはSNSやイベント、ウェブサイトで紹介して皆様に知ってもらう必要があります。
9. まとめ
振り返り: 自叙伝漫画制作のポイントのまとめ
自叙伝を書くポイントは「自由に書く」ことですが、起承転結をはっきりさせ、人生のターニングポイントを入れると、より深みのある漫画が完成します。
読者目線を意識して制作し、メッセージが読者に強く伝わっているかどうかを意識するようにしましょう。
読者へのメッセージ: 一歩踏み出す勇気と、自分のストーリーを共有することの大切さ
自身のこれまでのエピソードを漫画にして多くの方に知ってもらうと、同じような人生を歩まれている方や、壁にぶつかりなかなか前に進めずにいる方へも影響を及ぼします。自身の体験談からヒントを得られる方も多いはずです。
これまでの人生や経験を漫画を通して多くの方に知ってもらえると、読まれた方の今後の人生変わるキッカケになる手助けとなるでしょう。
10. よくある質問(FAQ)

質問例: 制作期間はどのくらい? どのようにアイデアを伝えればいい? など
Q1:制作費の内訳を教えてください
A:制作には複数人のスタッフが関わり、漫画のページ数やイラストタッチで費用は変動してきます。依頼する漫画家や企業と費用について確認しましょう。
Q2:低予算でも依頼は可能ですか?
A:作成は可能ですが、ページ数を減らす必要があるため伝えたい内容を精査する必要があります。
Q3:漫画家のタッチは選べますか?
A:種類がありその中から選ぶことは可能です。
Q4:漫画制作を依頼するにあたって準備しておくものはありますか?
A:初回の打ち合わせまでに、「何を漫画にしたいのか」「どんなターゲットに向けて作成したいのか」などをまとめておくと打合せがスムーズに進みます。
Q5:漫画化できない内容はありますか?
A:基本的に漫画にできない内容はありません。