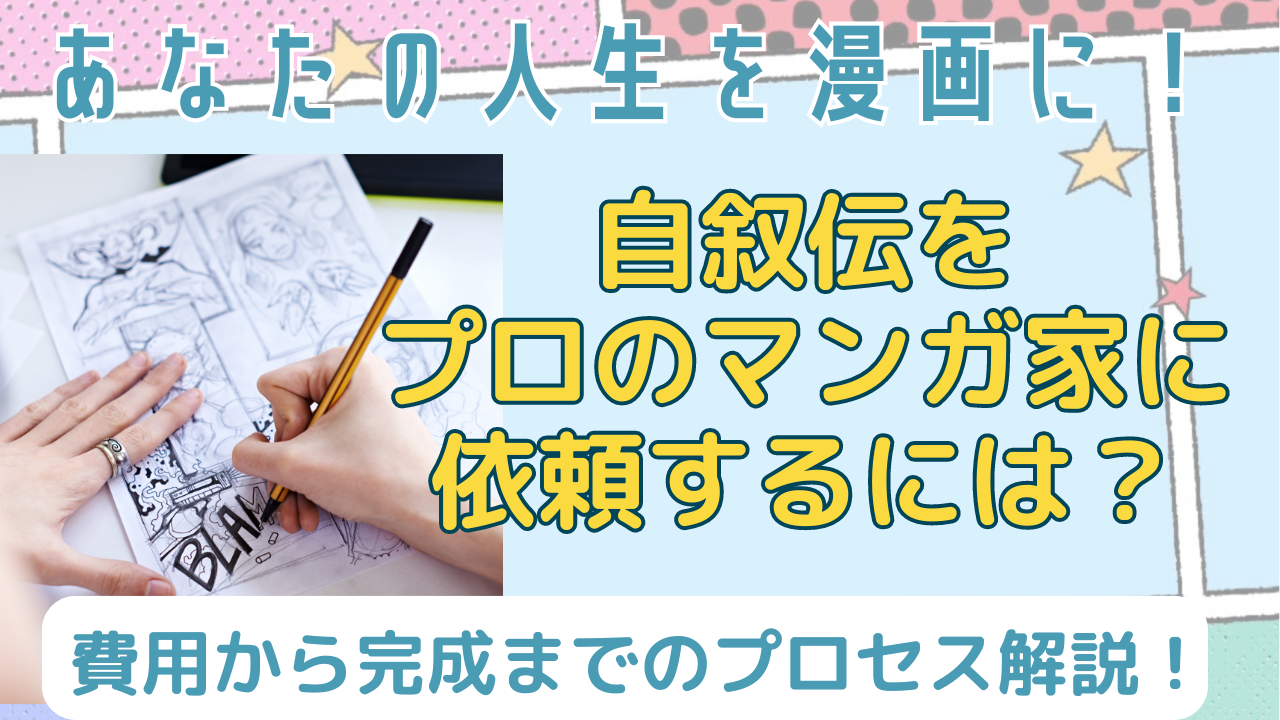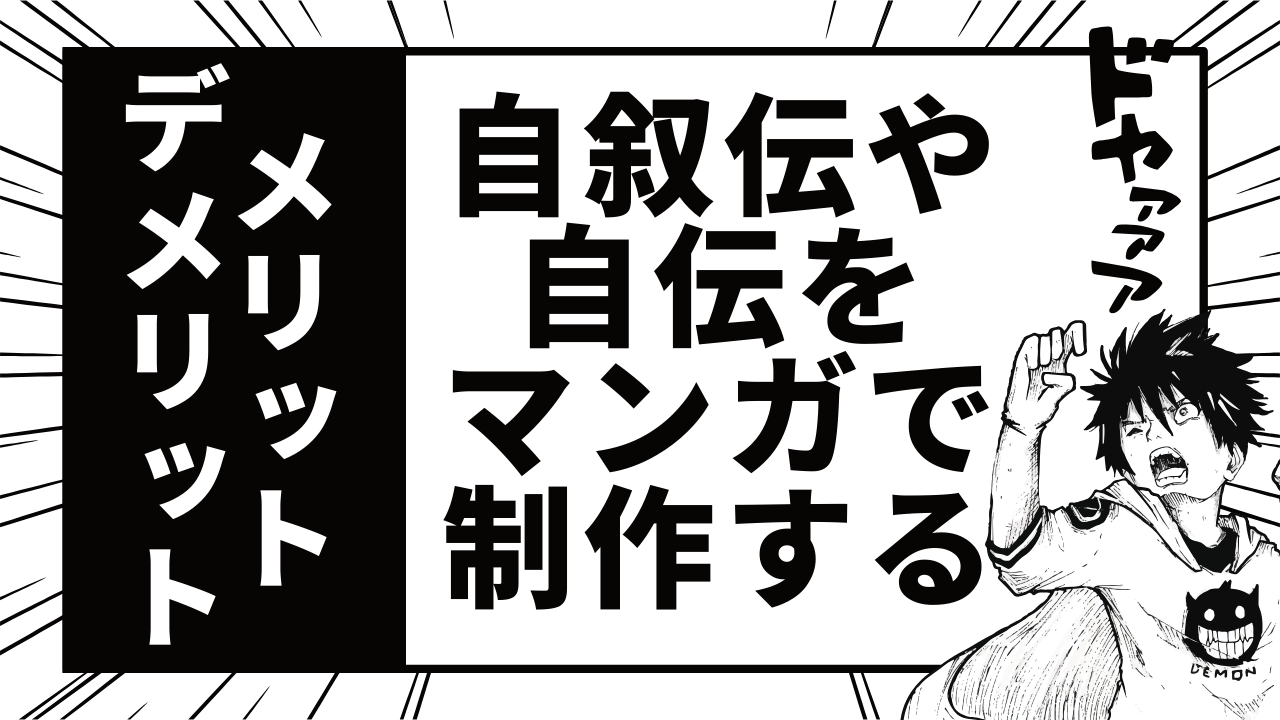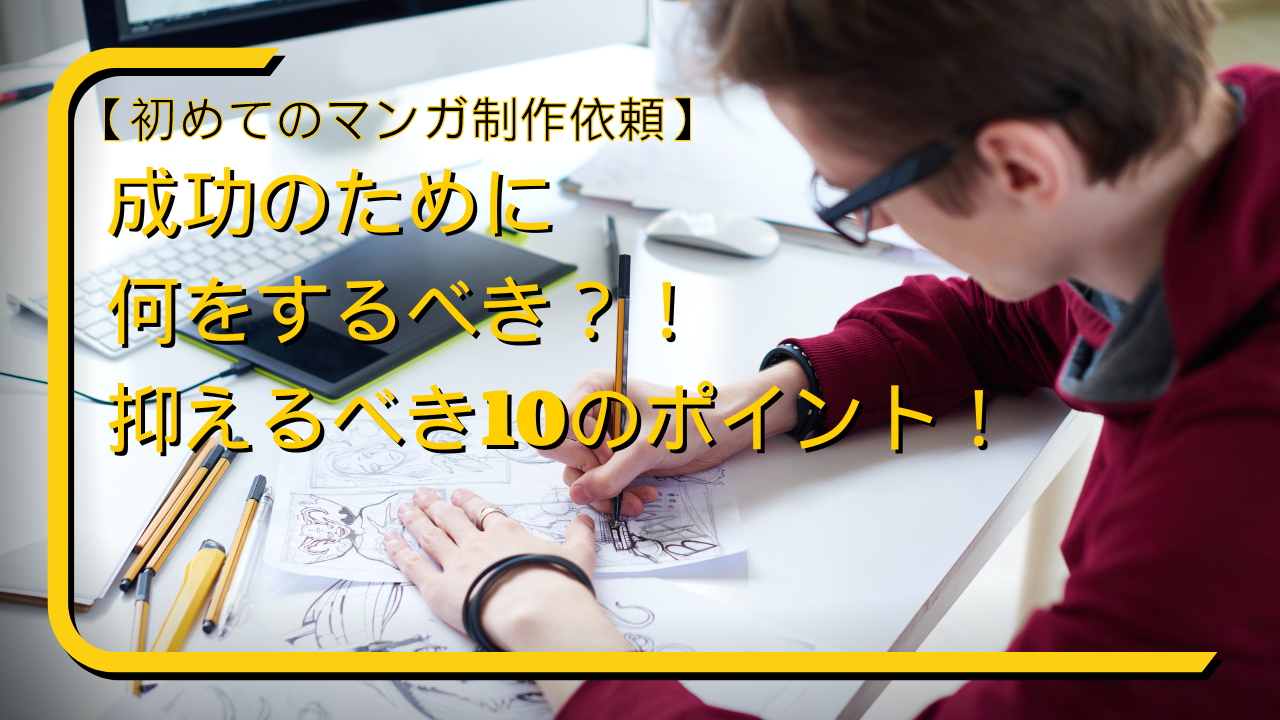
近年、オリジナルマンガの制作依頼を検討する人が増えています。これは、SNSの普及により、スマホで気軽にマンガが読めるようになったため、広告やPRの手法として活用されるようになったからです。
その一方で、マンガ制作を誰に、どのような方法で依頼すればいいのか。また、期間は予算はどれくらいかなど、初めてマンガの制作依頼をする場合には多くの悩みが出てくるでしょう。
そこで今回の記事では、マンガ制作を依頼する場合の流れや注意点について解説します。特に初めてマンガ制作を依頼する場合初心者に読んでいただけるように、基本的な部分から解説します。
これを読めばマンガ制作が初めてでも安心して依頼することができるでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
①目的と目標の明確化

依頼する際には、まずマンガ制作の目的と目標を明確にします。マンガ化する目的はなんなのかによって作成するマンガの内容は全く異なります。まずはマンガ制作を通して達成したいゴールと、そのための目標を設定していきましょう。
目標として設定するのは、自身がマンガをどんな媒体で利用するのかによって異なります。YouTube、ポスター、SNS広告、LP、チラシ、など様々なものがあります。自分が求めているマンガの完成系に近いものはどれなのかを決定し、その媒体でのマンガを完成させることを目標にします。
また、忘れてはいけないのが漫画はチラシなどと違い10年、20年と長く使い続けられるコンテンツです。設備投資の一環とも言えるかもしれません。あなたにとってどのような漫画が必要なのか、なぜ漫画がいいのか漫画制作自体の目標も明確化しておきましょう。
②予算の設定

目的と目標が決まったら、次は予算の設定に移ります。予算は多ければ多いほどいいですが、現実的に投資可能な金額を予算として設定していきましょう。一般的な相場は下記のようになっています。
- マンガ制作会社 15000円~30000円
- 個人漫画 8000円~15000円
- 有名な漫画家 数十万円
- SNSで有名な漫画家 50000円
- クラウドソーシング 6000円~12000円
- マンガ制作会社 20000円~40000円
- 個人漫画家 12000円~20000円
- 有名な漫画家 要相談
- SNSで有名な漫画家 要相談
- クラウドソーシング 8000円~15000円
このように制作費用は依頼先によって大きく変わります。では、それぞれの依頼先にはどのようなメリットがあるのか次の項目でみていきましょう。
③制作依頼先の選定

制作の依頼先には大きく分けて2種類あります。1つ目は制作会社です。会社ということもあり、依頼を忠実に、スムーズにこなしてもらえるでしょう。また、所属している漫画家のレベルも統制されていると考えられます。信頼も高く、依頼が初めての方でも安心できるクオリティが保証されているでしょう。
2つ目はフリーランスです。主にsnsで活動で活動しているため、フォロワー数により依頼価格が変わってきます。個人で行っているため、納期やクオリティは個人差があります。その分、細かいところまで時間をかけて丁寧に仕上げてもらえる場合もあります。また、snsの拡散力は計り知れないです。人気のあるマンガ家でしたらLP力も大きいと言えます。
【制作会社】
- 納期遅延トラブルになりにくい
- 一定クオリティが保証されている
- 相談の上、会社側から提案を行ってもらえる場合がある
- 依頼初心者の方には確実性があるためおすすめ
- チーム体制で行っているためコスト削減が難しい
- 細かい要望が通らない事がある
【フリーランス】
- 有名漫画家だった場合、LP力が高い
- フォロワー数により依頼価格が決まるため経費を格段に抑えられる場合がある
- 細かい指示も丁寧に対応してくれる場合もある
- DMでのやり取りが可能
- 完全に個人のためスムーズに計画が進まない場合がある
- コストは抑えられるが、クオリティーは保証できない
- トラブルがあった場合の対応が迅速に行われない可能性がある
また、依頼先のクオリティーを見極めるためにポートフォリオを提示してもらうことをおすすめします。
これまでの依頼者の評価を確認しておくと、どのような取引が可能か判断する材料になるでしょう。
ちなみに私のオススメはこちらの企業様です!
プロの漫画家さんが、直接やりとりしてくれて、あなたの世界観を一緒に表現してくれるとても素敵な企業様でしたよ!(筆者の私も依頼した経験ありw)
④ストーリーとキャラクター設定

マンガにおいて最も読者の興味を惹きつける部分がストーリーとキャラクターです。漫画家とヒアリングを通して、魅力的な構成を作っていきましょう。
【ストーリー】
独自のオリジナルのストーリーを作る場合、何を最終的に伝えたいのかはっきりさせておきましょう。物語の方向性、つまりゴールにより今後の展開の仕方が大きく変わってきます。漫画を作る上で最重要事項といっても過言ではありません。
依頼先の漫画家にエピソード等を話しどのような漫画にすればいいかを考えてもらいましょう。その際、大切なのは自分の予想と大きく違う事が殆どです。それは漫画家が依頼内容の漫画を読者に届くものとする為に沢山の工夫をするからです。では、どのような点を確認しながら制作を進めればいいのかというと。以下の3点になります。
- 目的と目標
- その漫画は理解しやすいか?
- 作家の良い所が出ているか?
漫画家に依頼する場合、作家のような作業をするというよりは「作家をプロデュースする」という感覚に近づけた方が最終的に漫画家の経験値を生かしたよい漫画が完成する確立が上がります。
【キャラクター】
登場人物が魅力的な漫画は読者が感情移入しやすいです。キャラクター作りに重要な要素は強い個性、弱み、意外性です。強い個性はインパクトを与えて他のキャラクターとの比較がしやすくなります。「主人公が特別な力を持っている」はよくあるパターンですよね。王道パターンだからこそ読者が惹きつけられるものです。
弱みとは、「俺様最強キャラは母親の前ではても足も出ない」というように一つだけ勝てないものがある。などの設定です。人間味があり、より共感性が高まるでしょう。
意外性は、「クールな一匹狼は猫の前ではデレデレ」「天真爛漫な女の子は実はサイコパス」など、実は〇〇。のような読者がびっくりするようなギャップを入れてみましょう。
- 強い個性
- 弱み
- 意外性
また、このキャラクターという部分は漫画の主軸になる大きな要素であり最重要項目の一つです。詰まりは漫画家との意識の共有が一番難しい所でもあります。何度も話し合い先のパートに進んでも何度も立ち返り時間を掛けてキャラクターを作っていく事でいくらでもその漫画が読者に届き訴求効果のあるくよいものになっていきます。苦しい作業ですが覚悟を決めし諦めずに良い作品を目指し追求する事をおススメします。
⑤シナリオと絵コンテ(ネーム)の制作

【シナリオ】
プロットにさらにセリフや明確なシーンを入れ、肉づけさせ、より完成に近づけていきます。しっかりシナリオを書くことにより、この後の作業がスムーズに行われます。
【絵コンテ(ネーム)】
漫画の出来は絵コンテ(ネーム)で9割が決まると言われています。シンプルさ、読みやすさを追求しましょう。
⑥契約と著作権の確認

【契約】
出版契約:83条1項 出版権の存続期間は当事者間の契約において定めます。存続の契約期間を取り決めていない場合、出版権設定後、初出版後から3年後に消滅します。
公衆配信契約:著作物の二次利用です。作品(マンガ)の翻訳出版、映像化、ドラマ化、舞台化、公衆配信でのデジタル化、広告イベントなどのビジネスを目的とした利用のことを指します。
著作物の二次利用の条件が自分かどうかをしっかり確認しておきましょう。きちんと話し合い、信頼できる代理人を選びましょう。売価ベース契約か入金ベース契約のどちらのパターンもあります。料率の高さがそのまま収入増にならないこともあります。紙か電子かという選択でも売れ行きが変わってきます。
公衆配信の期間と場所、方法もしっかり確認する必要性があります。デジタル化が進んでいる現代では容易に不正利用されてしまいます。不正利用のリスクを減らすために販売の場所を決めるのです。具体的な詳細を決めておけば、不正利用を炙り出すことができるでしょう。
【著作権】
著者には著作権という、独占的な権利があります。著作権法に守られ、第3者がいかにして作品を使用できるか言える権利です。
本という形で出版される場合は出版権があります。出版権者は6ヶ月以内に原稿を出版しなければなりません。
⑦制作プロセスの管理

漫画家とのコミュニケーションは大切です。ビジネスの会話も勿論ですが、雑談を交えてお互いの人柄を理解していくことも重要です。理解があってこそどのような仕事スタイルで進めて行きたいのか、現在はどのような心情なのか。など様々な要素が作品に影響して行きます。気を付けてほしい事として、クライアントが漫画家を製作段階で見下してしまうという事が頻繁に起こります。それはクライアントが想定していたものが漫画家が即座に対応するという事がほとんどの場合出来ないからです。クリエイティブやエンターテイメントの制作には時間がかかる事を元々から想定し信頼感を失わない努力も必要です。
⑧仕上げと修正
修正がある場合は早めにお願いしましょう。大きな変更はマンガが完成に近づくにつれて、修正が難しくなります。依頼先にもよりますが修正回数が決まっている場合もあるので、予測を持って正確に修正点を伝えていきましょう。漫画家とのトラブルになる場合もあるので事前に修正回数は決めておくと良いでしょう。お互いに気持ちよく取引を進めるために、確認は念入りに行いましょう。
⑨公開とプロモーション
紙媒体での販売、電子媒体での販売、どちらが売れていきそうか?というところを見分けていきましょう。作品のテーマから、どのような読者をターゲットにしているのか。この作品を見て、手に取った暁にはどんな心情になって欲しいのか。そういった目的を元に判断するのも良いでしょう。また、紙媒体と電子媒体どちらを選ぶのはどの年齢層かリサーチしてみると良いでしょう。漫画自体の訴求効果は拡散力とは別ですので、漫画制作の初期段階からマーケティングのプロを介入させておくのも一つの手段です。
⑩フィードバックと次のステップ
作品の反響を受け止め、分析することで読者の求めていることが現れます。マンガは読んでもらえる相手がいて完成するお仕事です。読者の貴重な意見が作品を進化させるといっても過言ではありません。漫画家との意見交換を経て何度も改善を重ねていき、2話、3話とより良いマンガを作っていきましょう。
まとめ
初めてのマンガ制作は夢のあるものです。実現には費用やリスクを考慮した上で堅実的な判断をしましょう。安定の制作会社か、費用を抑えた個人のSNS漫画家を選ぶのか、作品スタイルにあっている方と契約しましょう。
漫画家とのコミュニケーションは重要です。綿密な打ち合わせ、確認を行い方向性の一致を図りましょう。また、修正は早い段階で行い、終盤での大きな変更はないようにします。
契約書類は著作権、契約が自分にとって納得できるものであることを確認してください。
公開媒体が自分の発信したい方へ正しい方向性に進むのか考えた上で選択しましょう。
マンガは読者がいて完成する仕事です。フィードバックを行い作品をより良いものに仕上げて行きましょう。
ちなみに私的に、これらの10のポイントを網羅しておすすめするのがこちらの企業様です!プロの漫画家と直接お話ししながらマンガ制作を進めれるのでとても安心ですよ!