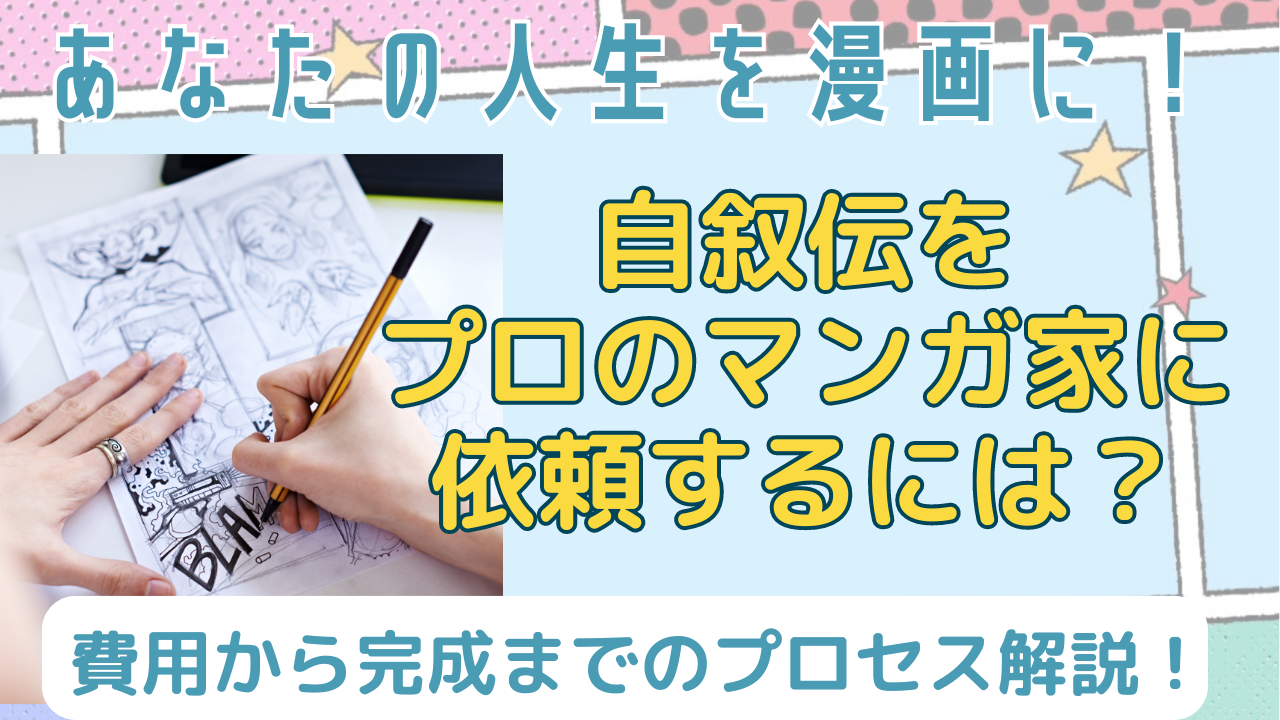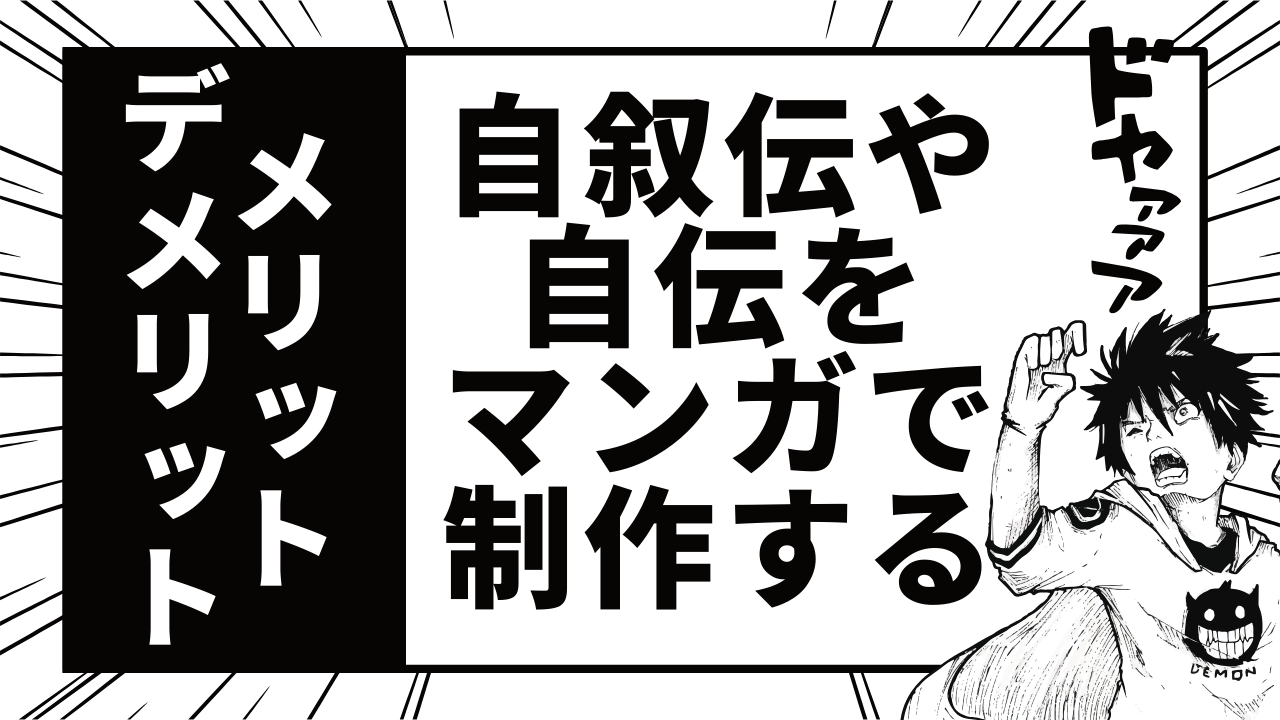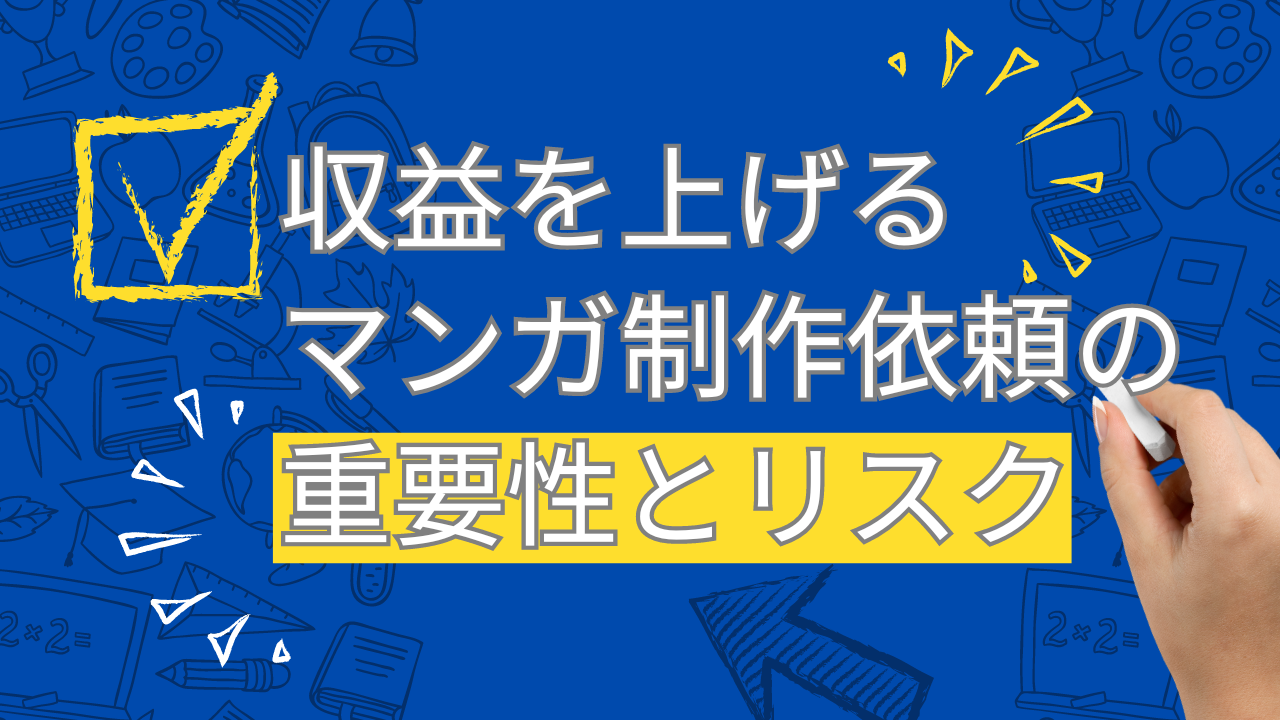
企業がマンガ制作を依頼し、収益を上げるマンガマーケティングという新しいビジネスモデルが話題になっていることをご存知でしょうか。
マンガを使うことで、視覚的にもわかりやすく情報を伝えることができるのが最大のメリットになります。
具体例をあげるなら、YouTubeで最近よく流れるようになった、ひげ脱毛の宣伝マンガがまさしくそうです。
あのマンガの宣伝効果の大きさを見ても、マンガマーケティングが、いかに有効なビジネスモデルかがわかると思います。
今回は、これから、マンガマーケティングを考えている企業向けにマンガ制作依頼の重要性とリスクについて話していきたいと思います。
これを読めば、マンガマーケティングを行う際の指標になること間違いなしです。
ぜひ、最後まで、読んでいただけると幸いです。
目次
明確な目的と目標を設定する

初めに、漫画制作の肝である目的と目標について、改めて確認していきたいと思います。
▷なぜマンガを制作するのか
企業が漫画制作依頼をする目的は大きく分けると、次に2つになります。
- 自社の商品やサービスを宣伝し、商品の購入やサービスのりようにつなげる。
- 企業のイメージアップを図るために行う。
この目的のためには、依頼するマンガ家に対して、自社の商品やサービスについて、詳しく話しておくことが大事になってきます。
▷目標とする成果やメッセージの明確化
目的を明確にしたら、次は具体的な目標を設定していきます。
例えば、マンガマーケティングを通して、月の売り上げを〇万円伸ばすなどです。
それと同時に、マンガ家に頼むときは、自社が伝えたいメッセージを明確にして依頼することが大事になってきます。
予算を適切に設定する

次は、予算についてお話しします。
▷制作費用の見積もりと予算配分
どこに依頼するかでマンガ制作依頼の費用が変わってきます。
- モノクロ1ページ:6,000円~1万2,000円
- カラー1ページ:8,000円~1万5,000円
- モノクロ1ページ:1万5,000円~3万円
- カラー1ページ:2~4万円
- モノクロ1ページ:数十万円(数万円)~
- カラー1ページ:要相談
- モノクロ1ページ:5万円~
- カラー1ページ:要相談
- モノクロ1ページ:8,000円~1万5,000円
- カラー1ページ:1万2,000円~2万円
一般に、マンガ制作には、このくらいの費用が掛かります。
ですので、それに合わせた適切な予算配分を行っていくことが肝要です。
コスト削減の方法と注意点

次に、コスト削減の方法と注意点についてお話しします。
▷コスト削減の方法
- 写真などの素材を用意する
マンガ制作には、素材集めの時間が必要なため、あらかじめ集めることで、制作者の時間短縮になり、コストの削減につながります。
特に、時間給で制作依頼をお願いしている場合には有効です。
- シナリオのプロットを用意する
基本シナリオを作成し、大まかなプロットや伝えたいメッセージをあらかじめ用意しておくことで、シナリオを作成する部分の費用が削られ、コスト削減につながります。ただ、シナリオを用意しても打ち合わせする中で全く違うシナリオにした方がいいという話になる場合もあります。基本シナリオはあくまでたたき台として制作しこだわらない事がおすすめです。プロと相談する材料と考えるのがベターです!
- ポートフォリオとしての利用を許可する
ポートフォリオ(ポートフォリオ内に新しい作品が入る事)は、(漫画家が)案件を受注する上で、有利に働くため、プロのマンガ家であっても、格安でお仕事を引き受けてくれる可能性が出てきます。ですので、ポートフォリオの利用の許可は、コスト削減の方法として、有効な方法です。
- 進行管理費があるか確認する。
円滑にマンガ制作を進めるうえで必要な費用を進行管理費と言います。マンガ制作会社やプロのマンガ家に頼むと進行管理費が発生するため、コストを抑えるのであれば、進行管理費が発生しない依頼先を選択することをお勧めします。
▷コスト削減の注意点
注意点として、コスト削減を重視しすぎたあまり、品質の低い作品が出来上がってしまえば、意味がありません。ですので、その点だけは意識して、コスト削減を行ってください。
信頼できるプロフェッショナルを選ぶ
マンガ家や制作会社の選定基準は、以下のようなものがあります。
- マーケティングの知識がどのくらいあるか
- 自社の商品やサービス商品やサービスをどのくらい理解しているか
- シナリオ制作は依頼先が行うのかそれとも外注なのか
- マンガやシナリオ制作の経験はどのくらいあるかマンガ実績が、宣伝したい自社の商品やサービスと合っているか
- 適切に予算は組まれているか
- 運用やサポート体制は整っているか
この6つの基準に照らし合わせて、適切なマンガ制作依頼先を選んでいくことが、肝要です。
ポートフォリオの確認と評価

依頼先のポートフォリオを確認することも重要です。
宣伝したい自社の商品やサービスのイメージと合致しているかを確認、評価し、依頼先を選択する基準の一つとします。
いくら、選定基準を満たしていても、自社の求める作品と依頼先のポートフォリオが、大きくかけ離れてしまえば、ミスマッチが起こり、双方にとって、不幸な結果を生んでしまう恐れがありますので、必ず、ポートフォリオは確認することをお勧めします。
漫画制作に入る心の事前準備

漫画制作において「漫画ならでは」「漫画制作が難しい(面白い)理由」を少し理解する事でより良い漫画を制作する事が可能になります。
▷漫画は事前に計画したストーリーにならない
漫画制作のほとんどの時間を占めるのがネーム制作という漫画の設計図(ラフ・絵コンテ)作りなのですが、漫画が良い方向に転べば転ぶほど事前に準備した計画からずれていく現象が起こります。漫画用語で「キャラクターが動く」という現象です。キャラクターの個性が漫画家の中に確立すれば確立するほど作家が描きたいようにはキャラクターが動いてはくれなくなります。漫画の主人公と漫画家でこの主導権を取り合うのが漫画制作の醍醐味で、この状態になると漫画はみるみる面白くなっていきます。漫画家は作品内の表現に制御が利かなくなった分、作品自体のテーマ性、制作目的を叶える事に専念する状態になり、結果読者に強いメッセージを送る事が出来るのです。これは漫画制作依頼により作られる漫画においてもとても良いことなのですが、その部分を認識している依頼者は少ないのが現状です。週刊少年誌等のプロの編集者などはこの「キャラクターが動く」まで漫画家に修正を出し続けキャラクターが動き始めるのを待つくらい重要です。
▷それゆえ大切なのは目的、伝えたいメッセージ
キャラクターが動き出せば物語は自然発生的に生まれてしまいます。そこを漫画家がどの視点から切り取るかに関わるのが「目的、伝えたいメッセージ」です。この部分だけは本当に明確に決めましょう。この部分を制作中に変えてしまう乱暴なクライアントが時々います。もちろん漫画は一からやり直し、キャラクターも動かなくなります。目的、伝えたいメッセージだけは絶対にブレない様にしましょう。
▷漫画制作において一番苦しい事「制作漫画が読めない」
漫画制作中に依頼者が一番苦しむ事は「製作者フィルター」ともいうべき目線でしか制作漫画を読めなくなる事です。制作者は作品を見る際に読者と同じ土俵からその作品を読む事が出来なくなるのです。新人漫画家が苦しむ事と一致します。プロの漫画家達は長い時間を掛けて「製作者フィルター」を外せるスキルを身につけますが、依頼者はそのような努力が必要な事をまず知らなかったり、自覚できなかったりするのです。するとどうしても漫画家が描いてくる漫画に不満を抱いてしまうのです。多くの場合「どうしてもっと話の内容を分かりやすく具体的に描かないんだ?」という疑問を持ちます。それは漫画の事を漫画に描かれている以上に情報を持っているからです。漫画家は情報を持たない読者が一瞬で理解できる程度の情報量に抑える工夫をしますので必ず意見がぶつかります。解決方法としては全くの第三者に漫画を読んでもらう事です。依頼者の感じている漫画の印象とは全く違った反応をしてくれます。ちなみに依頼者は制作した漫画を楽しむ、「製作者フィルター」を外して読む事は漫画家と同じ訓練をしない限り一生できません。何事においても当事者と部外者の感じる事が違うのと同じ事です。
依頼内容を具体的に伝える方法

具体的に伝えるポイントは次の2点になります。
- 制作する目的を明確にし、重要なポイントを整理して(しっかり)伝える。
- マンガ制作を通し、どういった成果をあげていきたいのか、目標を具体的にして伝える。
目的に応じた、ストーリーやキャラづくりが必要になってくるため、目的を明確にしておくことが肝要です。
また、目標を明確にすることにより、自社にとって最適な形の商品が作りやすくなる。そのため、目標を明確に伝えることが大事になってきます。
▷自社がアピールしたいことをイメージできる情報を明確にして伝える
広告漫画では、短編になるので、情報を詰め込みすぎると、読者にメッセージが効果的に伝わらないことが往々にして起きてしまいます。
ですので、必要な情報を精査し、短く、整理して、簡潔にまとめていくことが肝要です。
また、出来上がったものと自社のイメージが異なるというミスマッチを防ぐためにも、しっかり、アピールしたい情報を伝えることが重要になってきます。
しかし、漫画家も人間で、作家性がある為ミスマッチが多少は起こる事があります!そこを覚悟できていると良い漫画が提案された時にその漫画の良さに気が付くことができるでしょう!
この二つのポイントをしっかり押さえれば、依頼先と齟齬が起きない適切な資料の準備を行えますので、このポイントはしっかり意識して、準備に臨むことをお勧めします。
契約書をしっかりと作成する
次に、契約書について解説します。
契約書に含めるべき重要項目
以下の4つが契約書に含めるべき重要項目になります。
- 依頼内容
- 納期
- 報酬額
- 秘密保持契約
この4点に関しては、トラブルを事前に防ぐという観点から、必ず含めることをお勧めします。
また、秘密保持契約については、次の項の著作権と使用権の取り決めに密接に関わってくる重要な契約です。
注意点としては、両者が同意しないと結べないというものになりますが、後のトラブルを防ぐためにも、しっかり交渉して、お互いが納得する形で、契約を結ぶことが重要になってきます。
▷著作権と使用権の取り決め
完成したマンガの著作権は、依頼先の制作者に帰属します。
ですので、依頼先の制作者に無断で使用することは、法律に抵触しますので注意が必要です。
また、使用権については、依頼先に提示した目的に対してのみ発生するものですので、それ以外の用途に使う際は、別途、使用料を払って、使用することが肝要です。
ただ、依頼先によっては二次利用を許可しているところもありますので、まずは、依頼先としっかり交渉していくことが重要になってきます。
▷コミュニケーションを密に保つ
次に、コミュニケーションについて、解説します。
①定期的な進捗報告とフィードバック
まず、前提として、二つ以上の連絡先を交換しておくことをお勧めし ます。
速度重視であれば、音声通話を使える媒体で、契約内容重視であれば、チャットやメールなどのテキストメッセージで、信頼重視なら対面で行うなど、それぞれの目的に合わせて、適切なコミュニケーション手段を選択することが肝要です。
その上で、しっかりコミュニケーションをとって、打ち合わせを行っていくことが肝要です。
実のところ、それさえ守れば、それ以上の進捗報告やフィードバックは必要ありません。
相手は、プロですので、ある程度、自由に仕事をさせることが良い結果につながります。
心配かもしれませんが、相手を信頼する事も必要です。
②問題発生時の対応方法
相手は、プロですので、問題が発生することは少ないですが、金銭上のトラブルだけは起こりえますので、それを防ぐために、事前に、連絡先を2つ以上交換しておくことが肝要です。
また、どうしても心配であれば、事前に、対面で一度会っておくことをお勧めします。
この2点を守れば、大きなトラブルになることは少ないでしょう。
▷スケジュールを管理する
次に、スケジュール管理について解説します。
①制作スケジュールの設定と遵守
制作スケジュールは、マンガのページ数によって、以下のように変わってきます。
- 1p~4p:最短6~理想14日程度
- 8p~12p:最短2週間~理想40日
- 30p:最短40日~理想80日
※ネーム・下絵・仕上げの3工程あるので、それぞれ、×3倍になります。
ネーム制作に時間を使うほどいい漫画になる可能性は上がるので、原稿製作期間の2~3倍の期間はネーム制作に使っても良いかも知れません!
また、作業量によっても、スケジュールは変わってくるので、余裕を持ったスケジュール設定を組んでいくことが肝要です。
スケジュールを遵守するために、無理のないスケジュールを組むことが重要になってきます。
②納期遅れを防ぐための対策
長編漫画の場合は、一気に出すのではなく、各話を時期をずらして公開することを提案するのも一つの方法です。こうすることで、余裕を持って、制作を進めることができますので、納期遅れを防ぐ対策として有効です。
また、あらかじめ、スケジュール表を制作しておくことも有効で、これをしておかなければ、納期を守れないという事態が発生しやすくなります。
ですので、必ず、スケジュール表を作成しておくことをお勧めします。
ちなみに、スケジュール表は、用途によって、日ごとの物や月別の物など、様々なものがありますので、目的に合わせて、適切なスケジュール表を利用することが肝要です。
これらの対策をしっかり行えば、納期が遅れるというトラブルを未然に防いでいくことができますので、ひと手間かかることではありますが、面倒くさがらずに行っていくことをお勧めします。
▷修正リクエストを明確に伝える
次に修正リクエストについて、解説します。
修正点の具体的な指示方法
前提として、修正リクエストは、必ず、ネームの段階で行うことが肝要です。
それ以降の段階だと、修正ができないことや追加料金が必要になることもあるため、お勧めできません!
その上で、ネームの段階での具体的な修正点の具体的な指示方法を解説します
修正は、ネームの完成後に行います。
以下の3つのポイントを意識して、修正リクエストを行います。
- 自社のイメージや伝えたいメッセージと依頼先が制作したマンガの内容にミスマッチがないか?
- マンガの構成に不自然な点はないか?
- マンガが読者目線で、読みやすいものに仕上がっているか?
この3つのポイントを抑えて、必要な修正リクエストを行っていくことが肝要です。
そうすることで、自社と依頼先との間での齟齬が起きにくくなり、自社にとって適切なマンガ制作が可能になります。
ですので、修正リクエストは、この3つのポイントを必ず抑えることが重要です。
効果的なフィードバックの方法
前提として、自社の様々な立場の人を集め、多様な視点で、フィードバックを行うことが効果的なフィードバックにつながります。
その上で、以下のポイントを抑えることが肝要です。
抽象的な意見や主観の入った意見ではなく、客観的で具体的な意見を述べる。
自社の要望を明確にし、具体的に詳細に伝えることで、依頼先との齟齬が起きず、効果的なフィードバックを行うことができます。
ですので、必ず、フィードバックを行う際には、このポイントを意識してみてください。
▷最終チェックを徹底する
次に、最終チェックのポイントを解説します。
完成原稿の確認ポイント
前提として、ネームの段階で、修正すべき点はほとんど終わっていますので、
仕上げの段階でチェックする箇所は少ないということを頭に入れておいてください。
その上で、次の3つのポイントを抑えることが、肝要です。
- 仕上げの段階で加わった要素が違和感なく、描けているか?
- 誤字・脱字や描き込んだ内容に不自然なところはないか?
- 自社のメッセージが、はっきり強調されているか?
この3つについて、しっかり確認し、自社が求めるマンガ広告に仕上げていくことが、肝要です。
細部までチェックする重要性
実のところ、ネームの段階で、ほとんど決まってしまっていますので、ほとんど確認することはありません。
ただ、前述した部分は、見落としてしまうと致命的になってしまいますので、その点で、このような細部までチェックすることは、とても重要になってきます。
特に、誤字脱字や適切でない描き込みは、基本的な間違いではありますが、信頼を落とし、自社のイメージを大きく損なう結果につながってしまいますので、特に、良くチェックしていくことが重要です。
▷トラブル対策を講じる
トラブルについて、解説します。
よくあるトラブルとその対策
よくあるトラブルとその対策を以下にあげていきます。
- 納期が守られない
対策として、スケジュール表を作るなど、スケジュール管理の徹底、依頼先の負担を減らすために、事前に自社の方で、素材を用意するといいでしょう。
- 依頼先の都合で勝手に依頼をキャンセルする
対策として、キャンセルすることは防ぎようがないので、キャンセルされた場合は、ペナルティとして、キャンセル料を依頼先に請求するといいでしょう。
- 金銭トラブル
自社と依頼先の相互のコミュニケーション不足から、費用に対して、意見が食い違い、トラブルに発生することがあります。
ですので、そのようなことを防ぐためにも、事前に契約書を作り、契約時に費用を明確にするといいでしょう。
- 低クオリティの作品を制作される
依頼先のマンガ家の中には、クオリティの低い作品を出して、活動している人も中にはいます。
ですので、事前に、ポートフォリオや実績をしっかり確認するといいでしょう。
- 連絡がなかなか取れない
このようなことを防ぐためにも、お互いにとって都合の良い時間の確認と適切なコミュニケーション手段の確保をするとよいでしょう。
▷トラブル発生時の対応策
トラブルが発生した時は、お互いにしっかりコミュニケーションを取り、どちらかのせいにするのではなく、お互いに取って最善の形で、解決していくことが肝要です。
そうすることが、良い作品づくりにつながります。
マンガ制作依頼で失敗しないための総まとめ

最後に、まとめとして、マンガ制作依頼で失敗しない最大のポイントは、自社と依頼先とのスムーズなコミュニケショーン、これに尽きると思います。
結局、これができなければ、適切な修正リクエストもフィードバックも行えませんし、何より自社が宣伝したい商品やサービス、メッセージが明確に伝わらなければ、いかに優れたマンガ制作者であっても、いい結果にはつながりません。
また、トラブル発生時にも適切に対応できないです。
ですので、事前の準備とともに、適切なコミュニケーションを行うことは、当たり前のことですが、一番、大事なことになってきます。
企業の皆さんも、この記事を参考に効果的なマンガマーケティングに挑戦してみてください。
----------
社長の自叙伝を漫画で!会社案内を漫画で!広告を漫画で!
漫画のことならなんでも相談対応可能!
実際私も、注文したことがあるのですが、プロの漫画家さんが、二人三脚で親身になってクオリティの高いマンガを制作してくれますよ!
ぜひお問い合わせしてみてくださいね!